こんにちは。東北のフォトグラファーのzookomiです。
皆さんはSNSは資産という言葉を耳にしたことはありませんか?
それを聞いて、早速SNSのアカウントを開設した方も多いと思います。
しかし……
- Twitter(X)を始めたけど、どのように運営すればいいのかわからない
- 投稿したけれど、全く見てもらえない
- 他の人に絡むのはどこか抵抗がある
そんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
- Twitter(X)のプロフィールの作り方がわかる
- Twitter(X)での具体的な交流の仕方がわかる
- Twitter(X)での伸びる投稿のポイントがわかる
始めて間もない時やなかなか成果が出なくて最初はしんどいです。
 zookomi
zookomiしかし、上手く軌道に乗ればSNSは資産となります。
さらに運用のコツを掴めると楽しさもあり人間関係も広がります。
有意義なSNSライフを送れるように1つ1つ具体的に解説します。
人によって状況が異なりますし、どんどんアップデートされて状況が変わります。
「必ず成功する」という保証はできません。自分の実態に合わせて運用していただければと思います。
ちゃちゃっと結論を知りたい方のために、結論から
- 目的を持ち、伝わる明確なプロフィールにする。
- フォロワーさんなどとの良好なコミュニケーションを心がける。
- 有益性の高い情報や写真を投稿する。
- 継続する。
それでは行きましょう。
アカウントを育てるとかの前に前提の確認
まず前提をそろえます。
- インスタグラム、TwitterなどのSNSは0からのスタート
- 自分が撮影した写真やカメラの情報を発信するアカウント
- カメラの設定や現像の基礎は身に付いてきている
合うところや合わないところがあると思いますが、自分の状況に当てはめてみてください。
前提を見るとSNSを経験していないことから多少難しさはあると思います。
しかし、初めは誰もが0からのスタートです。
今回はTwitter(X)の運用についての解説です。
インスタグラムのアカウントが充実しているなど他のSNSが育っている場合は、育っているSNSと連携しながらTwitter(X)も育てていくことをお勧めします。
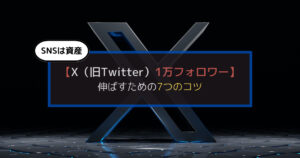
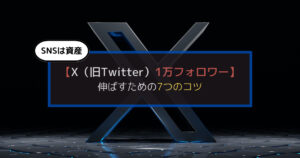
フォロワー0人ができる6つのこと
目的を持つ(明確にする)


皆さんがなぜSNSを頑張るのか
その目的をできる限り明確にして下さい。
なんとなく運用していても育たないのがSNS。
目的を明確化することで、アカウントの運用の方向性が決まってきます。
ちなみに私、zookomiの目的
「東北の魅力を知ってもらい、東北に来てくれる人を増やす。」
なかなか壮大ですね。(笑)
参考までに私の目的を書いたのですが、正直言うと上記の目的に辿り着くまで何度か変わってます。
定まったのも遅かったですし、これからも変わる可能性があります。
運用する中で方向性を決めていくのもありです。
しかし、目的を持つ、明確にすることは早い方が良いです。
できるだけ明確な目的を決めましょう。(後から変わっても大丈夫です。)



見にきた人が一目でわかるプロフィールを作る


プロフィールに書くことは次の項目を充実させると良いと考えています。
- どのような人物か
- どのような活動をしているのか
- どのような経歴を持っているのか
これらが一目見てパッとわかるのが良いでしょう。
もし仮に自分がフォローする立場だったらどのような方をフォローしたいと思いますか?
私がフォローする際に見ていることは次の通りです。
- 攻撃的な発言をしていないか
- 批判するにしても、健全な批判を心がけているか
- 独自の視点で写真を撮っているか
- 写真のクオリティが高いか
私は写真やカメラに関する情報を中心に発信するアカウントなので、フォローしようと思っている人が何を撮っているのか、どのようなことを心がけて撮っているのかなど、写真に対する気持ちや考えを主に見ています。
純粋に写真のクオリティが素晴らしいという方もフォローの対象になります。
つまり、自分がフォローしたい方のようにプロフィールを作り上げていけばいいのです。
では逆のパターンを考えてみましょう。
次に述べるような方はあまり積極的にフォローする気にはならないのではないでしょか?
- 自分のことしか発信していない
- 発信している内容に有益性がない
- 批判的な発言が多い
- 趣味などが大量に書いてあり、何をしているのかわかりにくいプロフィール
- フォロー数とフォロワー数の数が同じくらい
自分のことばかりで、他の人には無関心であるとか、批判的すぎるアカウントはフォローしたいとは思いませんよね。
4つ目に述べた趣味などが大量に書いている方は同じ趣味の方で繋がれる可能性もあります。
友達や知り合いを増やすという目的であればいいのかもしれません。
しかし、情報を発信する立場でアカウントを育てていくと考えたらどうでしょうか?何か違います。
フォローしている人が1000人や2000人などあまりにも多い場合やフォロー数とフォロワー数が同じような人数になっている場合だとフォローバックが目的の方だと感じたり、良い交流ができない方と思ってしまうので、フォローされる可能性は低くなります。
気になる人をフォローする


Twitter(X)を始めるとまず、おすすめ欄などに「フォローするのにおすすめ」のアカウントが出てきます。
しかし、何も考えずにフォローするのは好ましくありません。
「好みの写真を発信しているアカウント」や「自分にとって必要な情報を発信しているアカウント」をフォローしましょう。
始めはできるだけ自分のアカウントのジャンルに沿ったアカウントをフォローするといいです。
ただし、フォローのし過ぎは禁物です。
始めのうちは数十人ほどであればフォローしてもいいでしょう。
いい交流ができる範囲でフォローしていきたいですね。
フォローする方の中にはフォロワー数が数万人、数十万人いるいわゆるインフルエンサーの方もフォローすると思います。
インフルエンサーの方々の写真を投稿する際の工夫や、実践していることを学んでいくことは大切です。
マネできるところはどんどんマネをしていくことがSNSを軌道に乗せるポイントになります。



コミュニケーションを取る


Twitter(X)ではコミュニケーションが非常に大事だと言われています。
序盤は同じくらいの時期にスタートしたアカウントや同じくらいのフォロワー数の方、少し先を進んでいる方との交流を充実させていきましょう。
理由は、大きく2点あります。
- ともに伸びていくことができるから
- 交流の機会が増えるから
序盤にできた仲間は大切です。



共に切磋琢磨したり、交流することでさらに仲間が増えていきます。
コミュニケーションは引用とリプライを中心に
Twitter(X)上の人との関わり方は、大きく5つあります。
- いいね
- リツイート(リポスト)
- 引用リツイート(引用)
- リプライ
- DM
中でも特にお勧めなのは、③の引用リツイート(引用)と④のリプライです。
ここではコミュニケーションに関して詳しく解説していきます。
①引用リツイート(引用)のポイント
- 引用する方の写真やツイートに共感をするまたは投稿の内容を褒める
- 引用リツイートのし過ぎは禁物
引用リツイートすると、相手に通知がいきます。その方が自分の引用リツイートをリツイートしてくれる可能性があります。
リツイートするにしても皆さんがリツイートしたくなる内容はどのようなものでしょう?
きっと前向きな発言であったり、思わずリツイートしたくなる内容や写真だと思います。
喧嘩を売っていたり、悪口のような内容は他の方は見たくありません。
少なくとも私は見たいとは思いません。
表現の自由なので止めませんが、批判的すぎる内容は避けていきたいです。何もメリットはありません。
健全なコミュニケーションを取るためには良いところを自分なりに見つけて褒めたり、共感したりすることが大切です。
そうすることで、相手の方はリツイートしてくれる確率が上がります。
もしかしたら、プロフィール欄等にも目を通してもらえて、フォローにつながる可能性があります。
褒めることや共感することがないのに無闇に引用リツイートするのは、フォロワーさんのタイムラインを荒らすことにもなってしまうのでやめたほうがいいです。
大量に流れてくると、TLに引用リツイートが流れてくると
「邪魔だな。」とか、「またか。」とか
ネガティブな感情を抱かせる可能性があります。
引用リツイートのしすぎは禁物です。
②リプライのポイント
次にお勧めなのがリプライです。
リプライは気軽に交流ができる便利な機能です。
しかし、通りすがりにテロリストのように言葉の暴力を吐いてくる方もいます。
もし暴言を言われたら、ブロックやミュートをしてください。
リプライも引用リツイート同様、前向きな内容を意識しましょう。
もしかしたら返信してもらえないかもしれませんが、リプライをもらったら大体の方は目を通します。
少なくとも私は、リプライ等には必ず目を通すようにしています。
リプライも注意するべき点があります。特に大切な2点を挙げます。
- 節度ある健全な内容を心がける
- 教えを乞うような内容は避ける
毎回リプライをいただけるのは嬉しいですが、毎回同じような内容であったり、教えてもらおうとするだけの姿勢は好ましくありません。
返事をするのは案外時間がかかります。
良好な関係を築けたら知りたい内容も教えてもらえるかもしれませんので、地道に交流を図っていきましょう。
ポイントを押さえたツイートをする


写真アカウントの場合ですが、他のジャンルのTwitterの運用方法にもつながる場合があります。
参考になれば幸いです。
- 序盤に投稿するの写真の枚数は基本4枚組
- ハッシュタグはできるだけつけない
- 共感や情報を得られるキャプションをつける
解説をしていきます。
写真を載せる場合は基本4枚組
ご自身のアカウントの撮影スタイルによります。
基本は4枚を意識しましょう。
前述した、良好なコミュニケーションを心がけ、共感できるキャプションをつけていくと、必ずではありませんが伸びるときがきます。
しかし期待は禁物。
いきなり何万いいねがついたりしませんので、安心してください。(笑)
コミュニケーションを疎かにしていると、フォロワーの方に投稿が表示されなくなります。
これはTwitter(X)のアルゴリズムです。
いかにTwitter(X)がコミュニケーションを大切にしているのかがわかりますね。
コミュニケーションを図っていると、徐々に投稿にいいねがついたり、リツイートをしてもらうなどして徐々に伸びてきます。
そうすると少しずつですがフォロワーも着実に増えてくるはずです。
まだ手持ちの写真が少ないという方はまず、撮影の習慣を付けることが大切です。
準備する写真の目安としては自分の基準で大丈夫ですが、基準を示すとするなら、投稿に耐えられる写真が100枚あるのが理想です。
他の方法としては自転車操業のようになってしまうのですが、その日に撮影→その日に編集→その日に投稿の流れでも徐々に写真が増えてくるのでそれでもいいでしょう。
写真を撮っていくことも、地道に積み重ねていくしかありませんが頑張りどころです。
基本4枚組で投稿ですが、変化球的に1枚での投稿や2枚での投稿など投稿に変化を付けることも必要です。
1枚の方が伸びる場合もありますし、他の投稿方法でも伸び方は変わってきます。
私の勝手なイメージですが参考までに。
- 1枚はホームラン狙い
- 2枚や3枚は対比や物語性
このようなイメージで投稿しています。
フォロワーが増えてくると1枚が強かったり、必ずしも4枚での投稿でなくても伸び始めます。
必ず伸びるわけではありませんので、伸びないときは仕方ないと割り切りましょう。
キャプションによっても変わってくるので、キャプション次第というところでもあります。
最近ではバズリそうなキャプションをバズ構文と言われ始めています。
炎上のきっかけになるなど、あまりいい印象を持たれないので、使い過ぎには気をつけましょう。
ハッシュタグはできるだけつけない
ハッシュタグはできるだけつけない方がいいです。理由は2点あります。
- Twitter(X)はハッシュタグからの流入がほぼない
- 見る側にとっては閲覧の邪魔になってしまう
インスタグラムからTwitter(X)に来る方によく見られるのが、大量にハッシュタグを付けるというパターンがあります。
しかし、Twitter(X)はハッシュタグからの流入がほぼありません。
むしろ閲覧の邪魔になってしまいます。
そのため、できるだけつけないことをおすすめします。
基本つけなくていいのですが、次の場合はハッシュタグを付けるのもありです。
- 流行っているハッシュタグに乗っかる
- 何かのイベントが行われているとき
例えば、
- #〜チャレンジ
- #自分のおすすめのレンズを作例とともに載せる
このようなハッシュタグは、たまにであればいいと思います。
フォロワーが少ないときは、イベント系のハッシュタグをつけてみたり、駆け出しの人が仲間を見付けるためにハッシュタグを付けるのはありです。
ハッシュタグを付けていると、ハッシュタグを作った方からRTされたり、いろいろな方の投稿を見たりすることができます。
「共感できる」または「情報がわかる」キャプションを付ける
Twitter(X)はテキストベースのSNSなのでキャプションが大切です。
具体的にどのようなキャプションだと伸びるのか。
正直、正解はありませんが、次のようなキャプションを付けた投稿がよく伸びてるのを目にします。
- 〜のような〇〇
- 〇〇の本気を見た。
- 海外かと思ったら〇〇
繰り返しになりますが、最近ではバズリそうなキャプションをバズ構文と言われ始めています。
炎上のきっかけになるなど、あまりいい印象を持たれないので、使い過ぎには気をつけましょう。
ただ、見た方が「確かに!」「意外!」と思わせるような内容だといいですね。
また、場所などの情報を載せている投稿は大切です。
Twitter(X)は交流するにも良いSNSですが、情報を得るにも良いSNSだと感じています。
Twitter(X)を見ている方は、情報も必要としている方が多いです。
見た方が「行ってみたい!」や「得した!」という情報も載せていくとさらにいいですね。
例えば
- ◯◯でおすすめなスポット4選 その後箇条書きと写真を投稿
- ◯◯が良過ぎたのでみんなにも行ってほしい
などです。
見る側にとって必要な情報を載せていくことも大切になってきます。
継続する


最終的に継続が大切になります。
序盤はできれば毎日投稿が理想です。しかし、無理はしないようにしてください。
ただ、継続できる人が最後には生き残っている印象です。
継続は力なりですね。
続けていると思うことも出てきます。
自分と向き合いながら続けられるといいですね。
プラスα|認証バッジをつける(課金する)
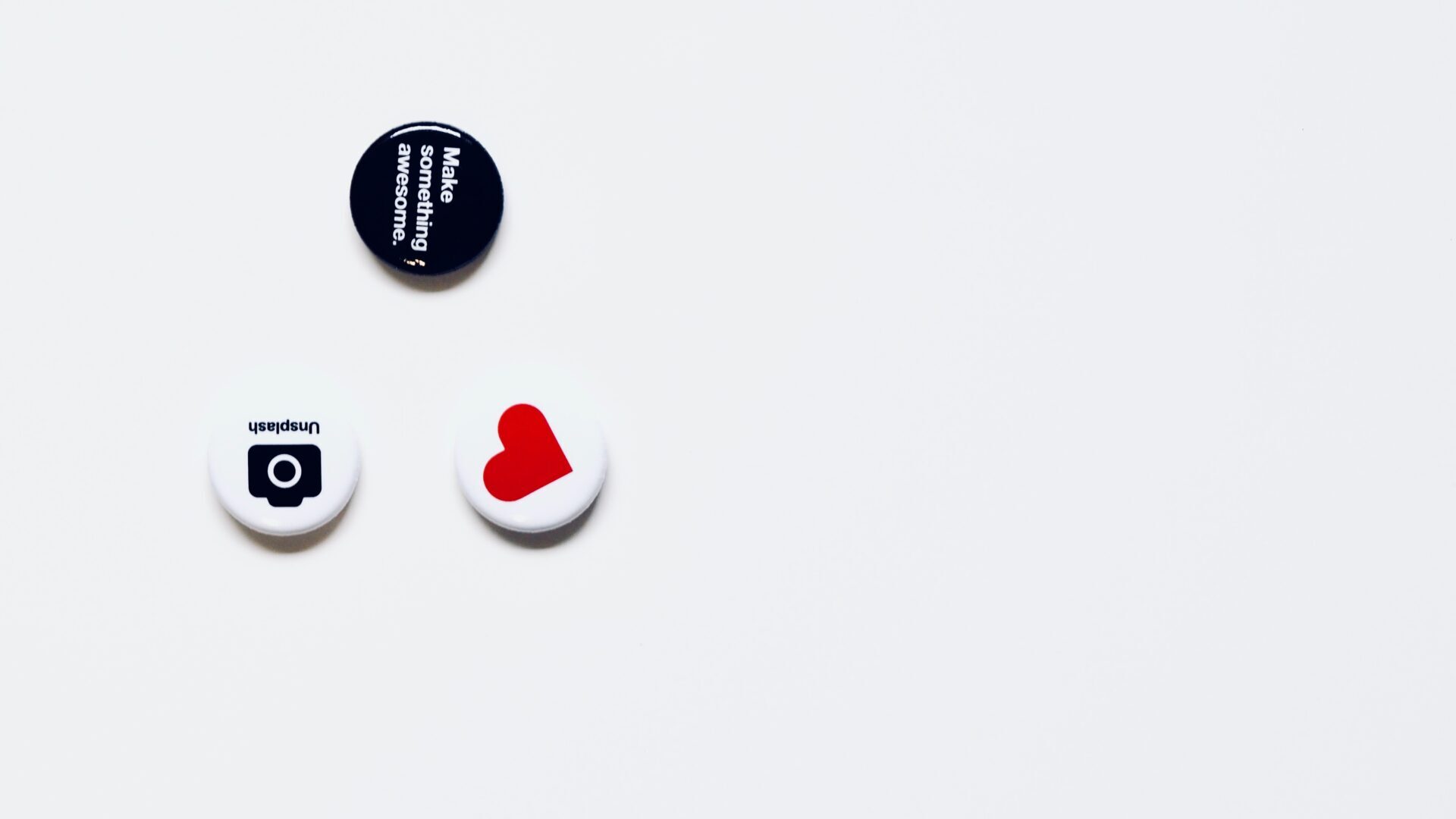
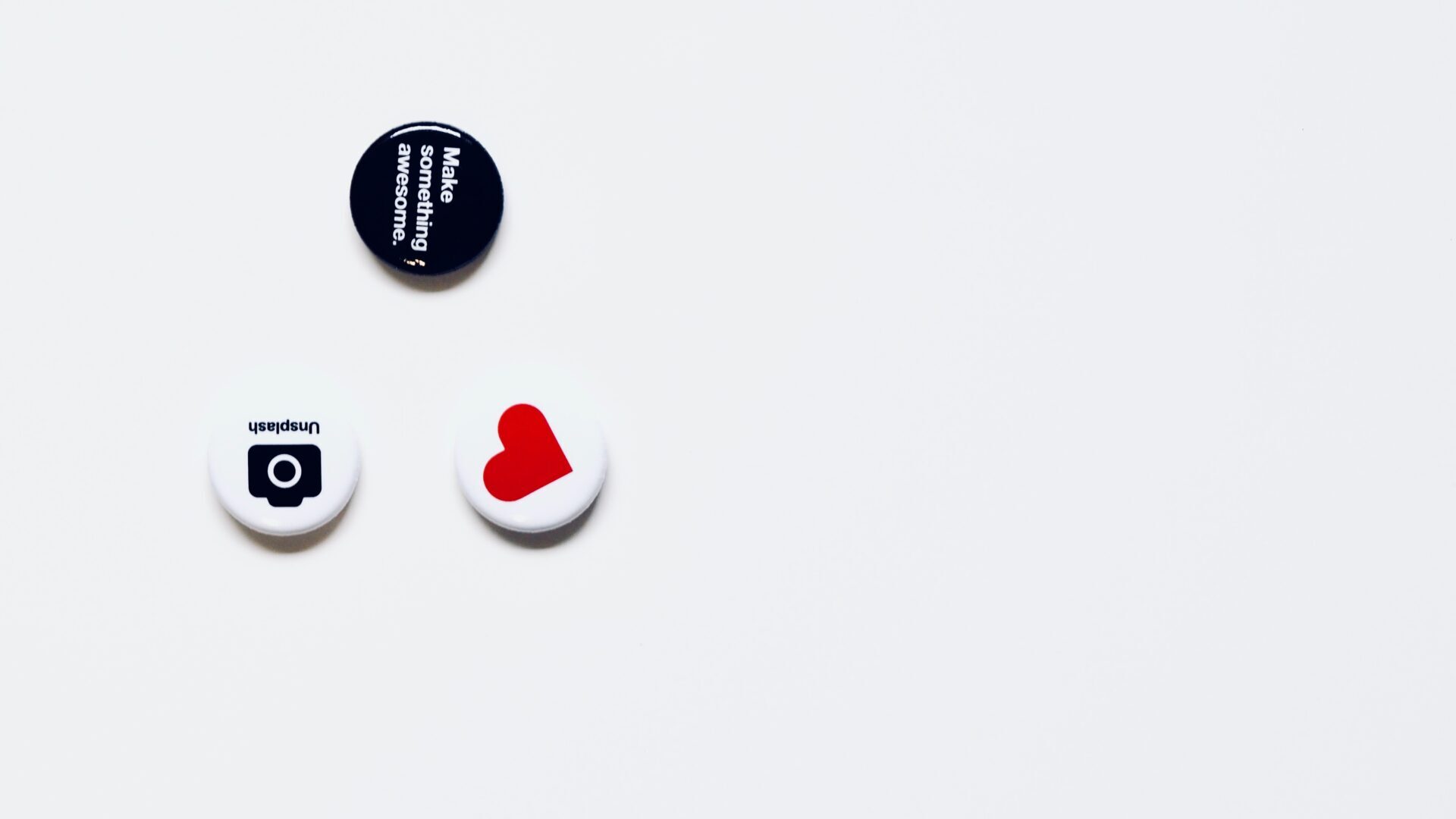
最近Twitter(X)では月額980円を払うと認証バッジを得ることができるようになりました。
認証バッジをつけることで、上位表示されやすく、リーチ数やエンゲージメント率の向上につながります。
爆速で成長させたい場合には認証バッジをつけるのもありです。
課金した金額以上のメリットを得られることもあるので、検討してみるのもありでしょう。
注意点
iPhoneアプリのTwitter(X)から申し込むと、月額約1300円になってしまうので、Appleを全力で応援したい人以外はブラウザから申し込むのがいいでしょう。
まとめ|良質な投稿を継続的に行うのが1番の近道
今回の記事のまとめです。
- 目的を持ち、伝わる明確なプロフィールにする。
- フォロワーさんなどとの良好なコミュニケーションを心がける。
- 有益性の高い情報や写真を投稿する。
- 継続する。
詳細を確認したい方はこちらから
最後まで読んでいただきありがとうございます。
最終的には、コツコツ継続していくことが鍵です。
SNSは現代の資産。
0→1にするのは大変ですが、伸びていくと様々なことにつながっていきます。
画面の向こうには人がいます。
画面の向こうの人を意識しながら、日々頑張っていきましょう。
もしわからないことや質問などがあれば「お問い合わせ」をお使いください。
0からスタートして、だんだんと伸びてきたらその後の伸ばし方も書いていますので、ぜひご覧ください。
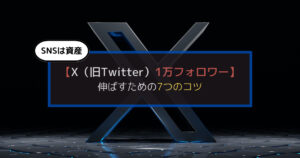
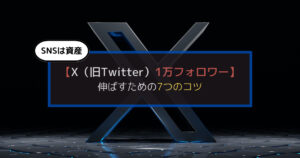
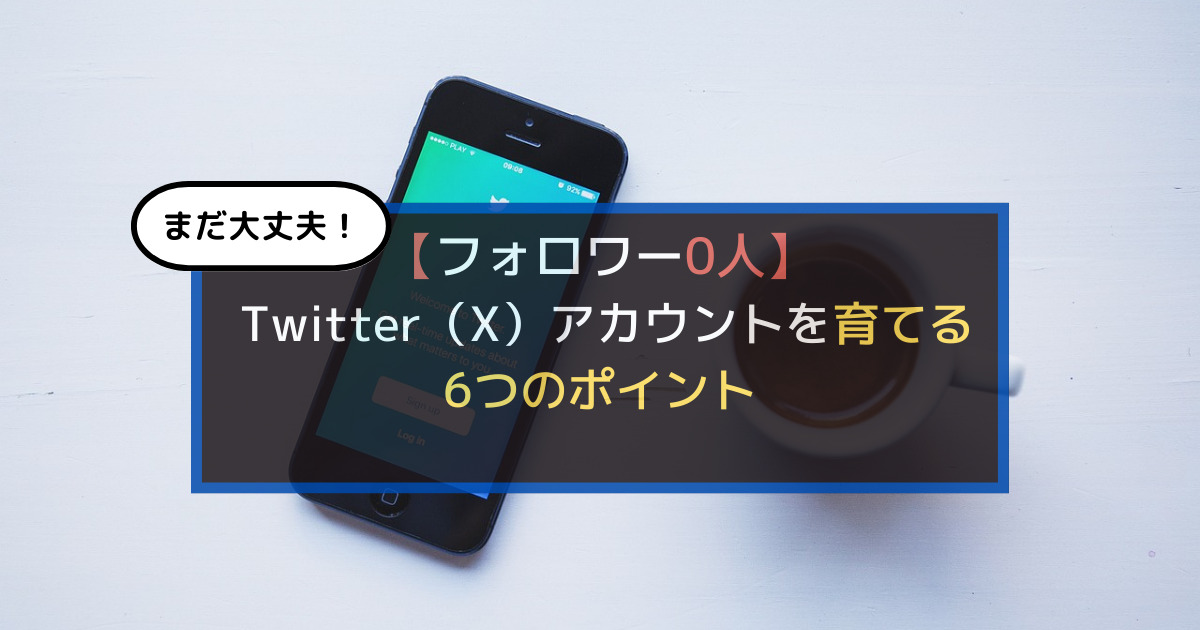


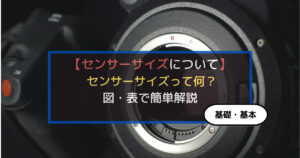
コメント
コメント一覧 (1件)
一目でフォロワーたくさんいることが分かる人のアカウント
その人は有名人ではないけど実際にフォロワーや、反応がたくさんある人。この人のアカウントを模倣して実験を行いました。その人の投稿をコピーペーストして自分のことのように演じるテストを行いました。この投稿を50回続けた結果、フォロワーは0人のままでした。
つまりあなたの言っていることは嘘であることがこの実験で証明されました。
あなたも私と同じことを実験して見て下さい。同じ結果になると思います。
この時のルールフォローバック目的のフォローは一切せず。フォロー自体も禁止です。